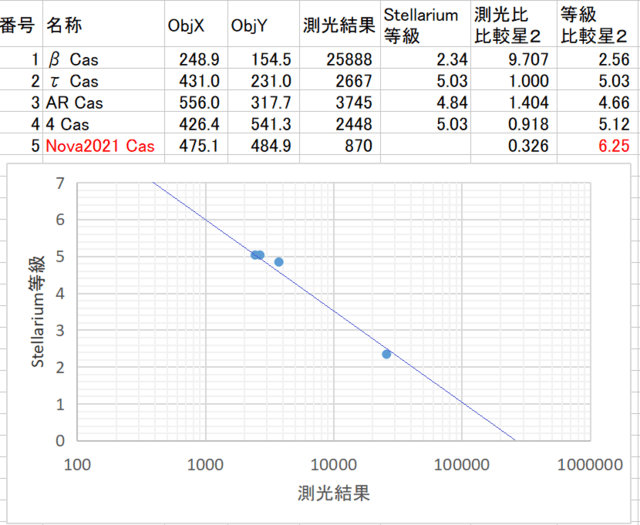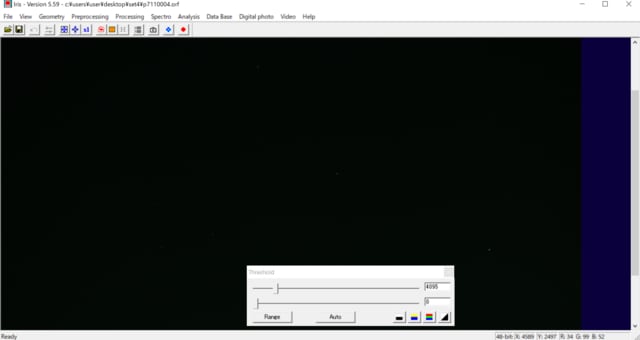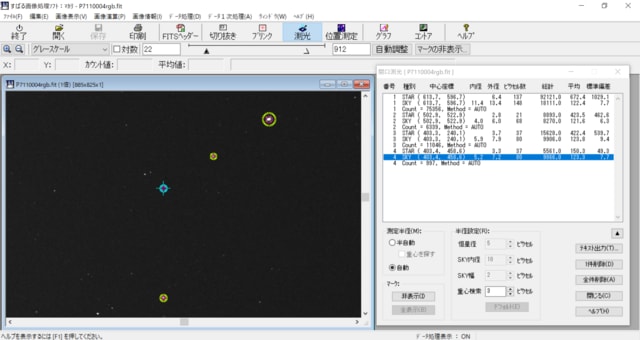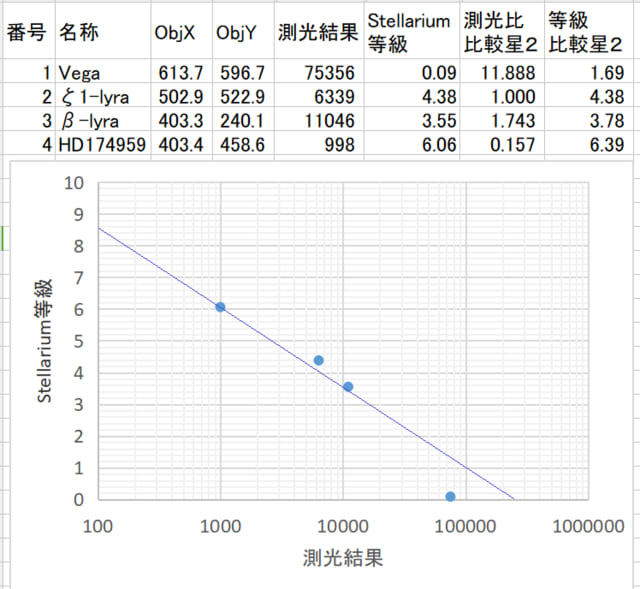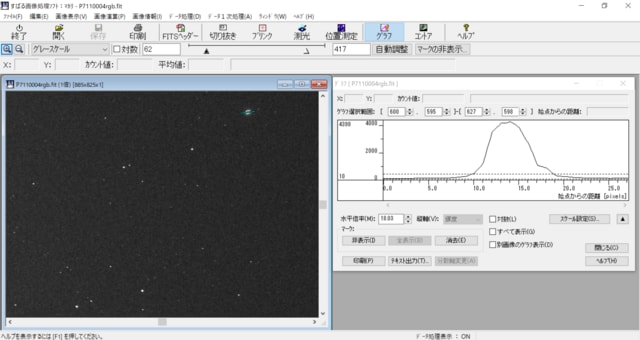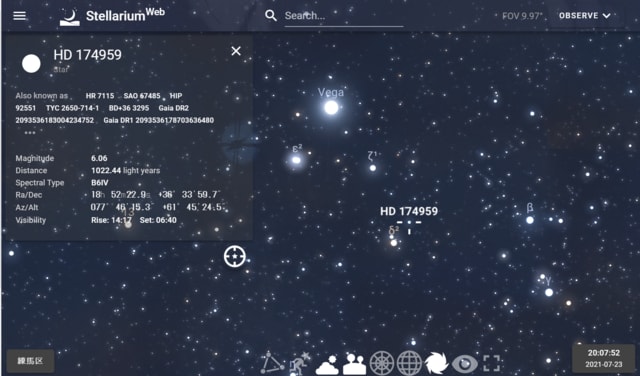今年の3月に撮影したシリウス[18-19]の画像[26]を、改めてマカリ[17]で分析した結果、シリウスB[20-22]を確認することができた。
(1)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影概要
・撮影対象
シリウス[18-22]
・機材
望遠鏡:MAK127SP 1500mm F12[1-4]
ファインダ:付属ファインダ(レッド・ドット式)
イメージセンサ:SV305[5-8]
架台:AZ-GTi赤道儀化マウント[14-15] 恒星追尾モード、ノータッチガイド
AZ-GTi制御アプリ:SynScanPro[16]
・画像処理
パソコン:WindowsノートPC(Core i5 2.30GHz 、8GB、240GB-SSD)
イメージキャプチャ:SharpCap3.2[9] 撮影時間:約30秒(約900フレーム)、aviファイル
スタック処理:AS!3(AutoStakkert!3)[10] 取り込みフレームの品質上位50%をスタック
Wavelet処理:RegiStax6[11-12] AS!3からの出力画像(tif)をWavelet処理
分析処理:マカリ[17] RegiStax6の出力画像(bmp)を分析、回転、切り抜き、グラフ機能他
(2)撮影結果(上が北)
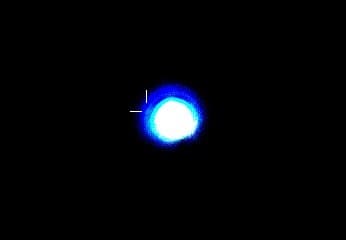
2021-03-10 20:21 シリウス
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 49ms, WB(B=216 G=100 R=128), 1920x1080, RGB24
※RegiStax6の出力画像(bmp)をマカリに読み込み、レベル調整後、シリウス部分を切り抜き
※露出49msの画像では、マークの部分にシリウスBが確認できた
・口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"[25]
・イメージセンサ分解能:0.80"相当[25]
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm[26])

マカリのグラフ機能(輝度分析)画面例
※シリウスAの中心から約27ピクセルの位置(離角:約11")にシリウスB[20-22]の輝度のピークが確認できる。
(3)まとめ
MAK127SPにSV305を取り付け、さらに、AZ-GTi赤道儀化マウントに搭載して、シリウスの直焦点撮影を試みた。
撮影した画像をマカリで分析した結果、露出49msの画像においてシリウスBを確認することができた。
参考文献:
(1)Maksutov Cassegrains
(2)マクストフカセグレン式望遠鏡-Wikipedia
(3)Sky-Watcher-Wikipedia
(4)Sky-Watcher Global Website
(5)SV305デジアイピースの使用方法
(6)SVBONY SV305 取扱説明書
(7)Svbony SV305 Camera FAQ
(8)SVBONY
(9)SharpCap
(10)AUTOSTAKKERT!
(11)RegiStax6
(12)RegiStax-Wikipedia
(13)ImageMagick
(14)Sky-Watcher AZ-GTiマウントレビュー
(15)AZ-GTi赤道儀化マウント-goo blog
(16)SynScanPro-GooglePlay
(17)すばる画像解析ソフト-Makali`i-配布サイト
(18)シリウス-Wikipedia
(19)連星-Wikipedia
(20)シリウスBにご注目 - 阿南市科学センター / 天文館 blog
(21)Sirius B-西はりま天文台
(22)シリウスの伴星Bを観測するチャンス到来!-EYEBELL
(23)今日のほしぞら
(24)Stellarium-Web
(25)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog
(26)IMX290NQV
(27)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影(54)-goo blog
(28)天体写真ギャラリー-シリウス
(1)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影概要
・撮影対象
シリウス[18-22]
・機材
望遠鏡:MAK127SP 1500mm F12[1-4]
ファインダ:付属ファインダ(レッド・ドット式)
イメージセンサ:SV305[5-8]
架台:AZ-GTi赤道儀化マウント[14-15] 恒星追尾モード、ノータッチガイド
AZ-GTi制御アプリ:SynScanPro[16]
・画像処理
パソコン:WindowsノートPC(Core i5 2.30GHz 、8GB、240GB-SSD)
イメージキャプチャ:SharpCap3.2[9] 撮影時間:約30秒(約900フレーム)、aviファイル
スタック処理:AS!3(AutoStakkert!3)[10] 取り込みフレームの品質上位50%をスタック
Wavelet処理:RegiStax6[11-12] AS!3からの出力画像(tif)をWavelet処理
分析処理:マカリ[17] RegiStax6の出力画像(bmp)を分析、回転、切り抜き、グラフ機能他
(2)撮影結果(上が北)
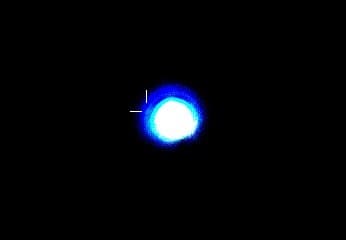
2021-03-10 20:21 シリウス
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 49ms, WB(B=216 G=100 R=128), 1920x1080, RGB24
※RegiStax6の出力画像(bmp)をマカリに読み込み、レベル調整後、シリウス部分を切り抜き
※露出49msの画像では、マークの部分にシリウスBが確認できた
・口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"[25]
・イメージセンサ分解能:0.80"相当[25]
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm[26])

マカリのグラフ機能(輝度分析)画面例
※シリウスAの中心から約27ピクセルの位置(離角:約11")にシリウスB[20-22]の輝度のピークが確認できる。
(3)まとめ
MAK127SPにSV305を取り付け、さらに、AZ-GTi赤道儀化マウントに搭載して、シリウスの直焦点撮影を試みた。
撮影した画像をマカリで分析した結果、露出49msの画像においてシリウスBを確認することができた。
参考文献:
(1)Maksutov Cassegrains
(2)マクストフカセグレン式望遠鏡-Wikipedia
(3)Sky-Watcher-Wikipedia
(4)Sky-Watcher Global Website
(5)SV305デジアイピースの使用方法
(6)SVBONY SV305 取扱説明書
(7)Svbony SV305 Camera FAQ
(8)SVBONY
(9)SharpCap
(10)AUTOSTAKKERT!
(11)RegiStax6
(12)RegiStax-Wikipedia
(13)ImageMagick
(14)Sky-Watcher AZ-GTiマウントレビュー
(15)AZ-GTi赤道儀化マウント-goo blog
(16)SynScanPro-GooglePlay
(17)すばる画像解析ソフト-Makali`i-配布サイト
(18)シリウス-Wikipedia
(19)連星-Wikipedia
(20)シリウスBにご注目 - 阿南市科学センター / 天文館 blog
(21)Sirius B-西はりま天文台
(22)シリウスの伴星Bを観測するチャンス到来!-EYEBELL
(23)今日のほしぞら
(24)Stellarium-Web
(25)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog
(26)IMX290NQV
(27)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影(54)-goo blog
(28)天体写真ギャラリー-シリウス